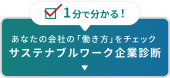日販テクシード株式会社
2025.3.26UP
■取組ポイント
コロナ禍を契機にワークスタイルを変革し、全社プロジェクトを立ち上げ。
ハイブリッド・ワークスタイルと育休制度の改善に取り組み、認定事業への登録を活用
AI技術やロボティクスを活用したシステム開発で、出版業界のみならず教育事業などにおける課題の解決にも取り組む日販テクシード株式会社。
コロナ禍をきっかけに新しいワークスタイルへの変革に舵を切り、全社プロジェクトを立ち上げました。さらに制度整備などに取り組んだ結果、「東京サステナブルワーク企業(みらワカプラス)」に登録されました。
プロジェクトを進めてきた経緯や、試行錯誤を繰り返す中で生まれた独自の取組についてお話を伺いました。

牧野玲さん
日販テクシード株式会社
住所:東京都中央区日本橋浜町3-3-2トルナーレ日本橋浜町 オフィス棟4F
業種:情報通信業
事業内容: ソフトウェア産業(システム開発・保守・運用)
HP:https://techceed-inc.com/

- 残業の少ない働き方の実現
- サステナブルな働き方・くらし方の普及
- 休暇を取りやすい働き方の実現
- 転勤に配慮した働き方の実現
- 多様な働き方の実現
- テレワークの推進
- 働く人が能力を生かせる賃金・処遇制度の実現
- 働きやすい就業環境の実現
コロナ禍をきっかけにワークスタイルの変革へ
―2020年7月に“New Normal”型ワークスタイルへの段階的な変革を会社の方針として打ち出し、9月には全社プロジェクトを立ち上げるなど、早い段階から働き方改革に取り組まれてきたそうですね。スピード感を持って変革を進めてきた経緯を教えてください。
コロナ禍がきっかけになり、今まで一部の従業員しか利用してこなかった時短勤務やフレックス勤務といった制度を全社的に使ってみようという機運が自然と高まりました。また、このタイミングで「ワークスタイルを変革しよう」と社長が決断し方針が打ち出されたことも相まって、プロジェクトの中で私たちの「ありたい姿」を模索していくことになりました。
―プロジェクトは具体的にどのように進めていったのでしょうか。また意見を集約する際に心がけたことなどはありましたか。
全社向けのアンケートはもちろん、部門別、役職別、拠点別などにディスカッションする場を設けるなど多角的なアプローチで課題や意見を洗い出し、共有しました。
リモートワークを例に挙げると、周囲との関係構築ができている社歴の長い従業員にとっては利用しやすい一方で、入社間もない従業員からは同僚と会えない期間が続くのは不安だという声がありました。その人その人で置かれている環境や経験も異なりますから、全員が納得することは難しいですし、全員の価値観が一致するなんてことはあり得ないですよね。
そこで、まずはすべての意見を一旦テーブルに並べてみて、それぞれが置かれている立場や持っている価値観に共感を寄せるという作業に時間をかけました。最終的には会社としてひとつの判断を下すことにはなりますが、この作業に時間をかけたことで従業員同士の相互理解が深まり、安心感をもって新しいワークスタイルに移行できたと感じています。
アナログとデジタルのいいとこどり―ハイブリッド・ワークスタイル
―プロジェクトでの試行錯誤から生まれたのが出社とリモートワークの両方を取り入れたハイブリッド・ワークスタイルとのことでしたが、どのような経緯を経て運用に至ったのでしょうか。

弊社はチーム単位で業務を進めていくプロジェクト型のシステム開発が中心の業態なので、在宅で集中して開発に取り組む時間も大事ですが、メンバー間での連携が取りやすい関係性を築く必要もあります。しかし、コロナ禍で半ば強制的に始まったリモートワークが長期化するにつれて、入社間もない従業員が孤独を感じるようになったり、業務を抱え込んだ従業員が体調を崩すケースも出てきました。
コロナ禍の波に合わせて出社調整を行う中で、せっかく出社してもチームメンバーに会えないという声も聞かれるようになったため、チーム単位で曜日を決めて出社するチーム出社をルール化しました。
また、2021年に本社を全面リニューアルし座席はフリーアドレス化としたのですが、チーム出社がしやすくなるような工夫として、座席予約ツールを自社開発することでプロジェクトのメンバーが同じエリアにまとまって席を確保できるようにしました。
―現在のハイブリッド・ワークスタイルに対する従業員の反応はいかがですか。
運用開始当時は出社を面倒に感じる従業員もいたようですが、現在では特に若い従業員から同期に会うことや、ランチタイムを一緒に過ごせることが楽しみだという声が聞かれます。出社することで他の従業員との繋がりを感じることができると、業務を進める上でも心強いですよね。
「女性の育休」から「男性も育休へ」
―男性従業員の育休取得率向上にも力を入れているとのことでしたね。育休取得への意識はどのように高めていったのでしょうか。
弊社はもともと女性比率がIT業界としては高く、女性従業員の育休復帰率はほぼ100%と高い水準にありました。ただ、育児休暇は女性が取得するものというイメージが社内で浸透しており、男性の利用者がいない状態でした。
弊社で初めて育休を取得した男性従業員は1週間だけの制度利用に留まった上に、休暇中に業務の対応をしてしまうなど、制度を上手く活用できたとは言えない状況でした。
そこで、育休取得対象者本人が上司と交渉するのではなく、人事担当者も同席して説明に入るようにし、長期間業務を休むことへの抵抗感をやわらげる工夫をしました。また、これまで産休育休を取得する女性向けに作成していたハンドブックを、制度や給付金の解説を盛り込み男性用にも作成し配布しました。これらの取組により、男性従業員も育休を取得できるという認識が社内で浸透して、期間を分割しての取得や長期間の取得など上手く制度を活用するケースも出てきました。
認定制度を活用することで企業の健康診断を
―今回「東京サステナブルワーク企業」認定に向けて、何か新たに取り組んだことなどはありましたか。
2022年(令和4年度)に東京都の「ライフ・ワーク・バランス企業」の認定は取得していたので、すでに取り組めていた分野は多かったのですが、定年延長や副業・兼業についてはまだ制度が整備できていませんでした。今回、認定を受けるための挑戦が、足りていない部分を認識し、今後制度整備に取り組むきっかけになりました。
こういった認定制度の要件項目を確認すると、優良企業として認定されるためにはどこまで取組を進めていないといけないかということを改めて認識することができます。また、人材確保という面でも、弊社の達成できている部分を分かりやすく学生や求職者にアピールできるというメリットがあります。社内向けには従業員が安心して働き続けるための安心材料になりますし、今後さらに取組を進める上で足りない部分を経営陣に明示する機会としても活用できます。
―今後はどのような展望をお持ちですか。

ここまでプロジェクトを推し進めてきて思うのは、働き方改革で従業員の働きやすさは改善しますが、それだけではなく働きがいを感じてもらいたいということです。そのためには、従業員自身が成長を実感できるようなフィードバックや育成を受ける機会が必要です。現在のハイブリッド・ワークスタイルにおいて、従業員が相互にそういった成長を実感しあえるような環境をさらに整備し従業員の成長を後押ししていきたいです。
また、世の中は変化し続けているので、それに合わせた柔軟な対応を模索することが企業には求められます。その変化を成長のチャンスと捉えて前向きに取り組んでいけるようなバックオフィスでいたいですね。特に本事業のような認定制度には、企業版の健康診断を受けるようなイメージを持っているので引き続き積極的にトライしていきたいです。
―最後に、現在働き方改革に取り組む企業へのメッセージをお願いします。
以前の認定制度で、同時期に認定を受けた企業の担当者と知り合い、お互いに情報を交換していました。どのように働き方改革を進めたのか話を聞いたり、オフィス見学に出向いたりなど参考になりましたし、刺激を受けました。他社でも働き方改革に向けて頑張っている仲間がいるのだと心強く感じました。ぜひ、本事業のような認定制度を通じて企業の成長機会としていただきたいし、一緒に取り組む仲間を見つけてほしいです。
―ありがとうございました。
インタビューを終えて
ハイブリッド・ワークスタイルについてのお話では、あえてアナログな出社スタイルも維持することで結果的にチームとしてのパフォーマンス向上に寄与しているという点が興味深かったです。
インタビューの最後には「働き方改革に終わりはないですね」とお話された牧野さん。認定制度を企業版の健康診断と捉え、前向きに取組を続ける姿勢が印象的でした。