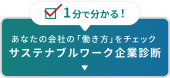株式会社アクシオ
2025.3.26UP
■取組ポイント
従業員主体の働き方改革プロジェクトチームを立ち上げ、各課題に対して一つひとつ丁寧に取り組み、制度整備や推進を行いながら、会社全体で更なる働き方改革を推進
テレワーク制度は、IT業界であれば導入しやすいだろうと思われがちですが、円滑に進めていくためには地道なルール作りが欠かせません。
「みらワカプラス」に登録されている「株式会社アクシオ」は、ID管理やユーザー認証などの統合認証基盤分野において国内トップレベルの構築実績を誇るITソリューション企業です。
早くから従業員による働き方改革プロジェクトチームを立ち上げ、テレワーク制度を推進してきました。制度を定着させるための工夫や改善を続ける取組についてお聞きしました。
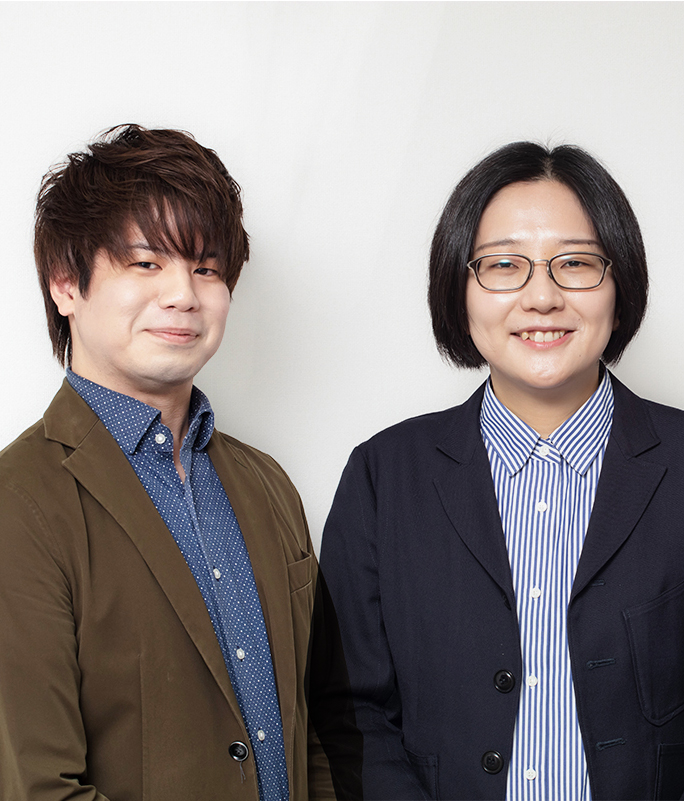
竹内 柾貴さん
認証基盤技術部副部長
井上 七保子さん
株式会社アクシオ
住所:東京都品川区西五反田2-12-19五反田NNビル5F
業種:情報通信業
事業内容: ITソリューションの提供
HP:https://www.axio.co.jp

- 残業の少ない働き方の実現
- サステナブルな働き方・くらし方の普及
- 休暇を取りやすい働き方の実現
- 転勤に配慮した働き方の実現
- 多様な働き方の実現
- テレワークの推進
- 副業・兼業の推進
- 働く人が能力を生かせる賃金・処遇制度の実現
- 働きやすい就業環境の実現
働きやすい会社をテレワーク制度で実現させたい!
―2017年に社内で「働き方改革プロジェクト」のチームを発足されたとのことですが、きっかけは何だったのでしょう。

井上さん 働き方改革が進む社会の動きに合わせて、IT企業として次世代に向けてどのようなソリューションを取り扱っていくべきかを考えていました。そして、そのような動きに合わせてまずは社内でも働き方改革に向けたプロジェクトを立ち上げようと、営業や企画、技術、総務など全部署から1名ずつ計12名のメンバーで動き出しました。
最初はソリューションの開発がきっかけではありましたが、働き方改革を通じて会社全体として働きやすい環境をつくること、従業員のライフ・ワーク・バランスを向上させることを目的として取組を進めてきました。
―働き方改革を進める前は、どんな課題を抱えていましたか。
井上さん 多くのIT企業では長時間労働が課題となっていましたが、当社も従業員の労働時間がかなり長い印象がありました。
そこで、プロジェクトメンバーで課題を深掘りしたところ、テレワークを有効活用できていないのではないかという話に焦点が当たりました。
もともとテレワークできる環境は整っていたのですが、実際に活用できていたのは全従業員の10分の1ほどでした。そのため、誰でもテレワークを使えるようにして、長時間労働とテレワーク利用の偏りを解決しようと、テレワークの制度化を進めることになりました。
新たに出てくる課題をひとつずつ乗り越えて
―そもそもテレワークできる職場環境にあったと話されていましたけれど、それでも活用できなかった原因は何だったのでしょう。

井上さん 従業員がテレワークを利用する上での障壁はいくつかありました。そのひとつは、テレワークを申請する際に上司へ都度相談する必要があったことです。
また、テレワークでできる業務が従業員や部署によって差があったことで、利用状況に偏りが生じていました。例えば、稟議書など紙の書類による決裁が多い営業部は、会社にある書類に押印が必要で、出社する機会が増えてしまいます。
―テレワークの利用へ向けた様々な障壁をどう解消していったのでしょうか。
井上さん まず、上司への相談を不要にし、利用時の心理的ハードルを下げました。また、申請方法も簡素化しました。具体的には、テレワークを実施する前日までにグループウェアの個人スケジュールに明記し、オンライン上のワークフローでテレワーク申請をするだけで利用ができるようにしました。
上司への相談が不要であるかわりに、相談や来客など、対面でのコミュニケーションが必要な場合は、事前に上司が部下に連絡して、出社してもらうようにお願いするなど工夫をしています。
同時に、テレワークを阻害する要因を明確にするため、月に1回、全従業員を対象にアンケートを取り、社内環境の整備も進めました。無駄な会議の削減や業務の棚卸を行い、従業員や部署間での業務の偏りを極力減らすよう努めました。また、クラウド決裁システムやウェブ会議ツールを導入したことで、よりテレワークの利用率が上がりました。
―制度を導入したあとに見えてきた課題はありましたか。また、その課題に対してどのように取り組んでいったのでしょうか。
竹内さん テレワーク制度の利用率が上がるにつれ、業務量のバランスが課題となってきました。テレワークをしている従業員が本来やるべき社内の仕事を、出社をしている従業員が代わりに負担するという事例が出てきたのです。
井上さん この課題の解決策として、テレワーク制度のガイドラインを策定しました。細かいルール作りはもちろんですが、テレワークは権利ではなく、あくまで業務を円滑に進めるために導入したものです。テレワークが目的ではないということを従業員に理解してもらうことが大事でした。
ガイドラインができたことで、みんながテレワーク制度の意図を理解した上で利用してくれるようになりました。また、掲示板にガイドラインを掲載し、従業員が常に確認できる状態にしました。そして、さらにガイドラインの周知と理解を促すために、半年に1回の全社ミーティングでも改めて説明する場を設けています。
―IT企業なのでテレワークの制度化もスムーズに進みそうなイメージがありましたが、制度化を進めるにあたって感じた課題はありますか。
井上さん 管理職もテレワーク制度の大枠には賛成で、制度化についてはスムーズに進みました。その一方で、部署によってどうしても譲れないことが異なり、管理職と私たちの意見が細部で食い違うということがありました。そういった意見の調整に時間がかかりました。
現場の担当者が望んでいても、管理職が首を縦に振ってくれない限りは何も始まりません。当社では、月に1回、プロジェクトの役員報告会があって、役員が気乗りしない話や耳が痛い話だとやんわり断られたりします。それでも2、3か月後にもう1回、伝え方を変えて提案すると、また少し違った反応が返ってきたりします。その繰り返しで、粘り強く進めてきました。
管理職も巻き込んで、さらなる働き方改革を
―テレワーク制度を定めてから7年が経ちました。月平均労働時間が166時間と残業の少ない働き方が実現できているのは、テレワーク制度によるところが大きいのでしょうか。

竹内さん 現在の残業の少ない働き方は、テレワーク制度に加え、ウルトラシフト勤務制度(時差Biz)の導入、コロナ禍の在宅勤務の広まりなどが重なりあった結果だと思います。
コロナ禍が明けて出社制限はなくなりましたが、今もテレワーク制度を利用する従業員は多く、制度としてかなり定着しました。当初から目的としていた、ライフ・ワーク・バランスがとれた働き方が少しずつ実現してきていると感じています。
―従業員のライフ・ワーク・バランスの向上へ、さまざまな取組をされてきたかと思いますが、今後さらに取り組んでいきたいと考えていることはありますでしょうか。
竹内さん 当社の月平均労働時間や有給取得率は「東京サステナブルワーク企業」の登録要件をクリアしていますが、あくまで全従業員の平均値です。まだ従業員や部署の間で偏りがあるので、休暇の取りやすさ、業務量の平準化を進めて改善していきたいです。
井上さん これまでの働き方改革は、様々な取り組みや制度を従業員から会社全体へと広めてきました。その中で実感したのは、最終的に直面する壁が「管理職の意識を変えないと根本的な問題が解決されない」というところです。
2024年12月から、管理職が集まって会社の将来について話し合う活動がスタートしました。10年後もアクシオがお客様に選ばれ続けるためにはさらに今の考えを刷新していかなければと考えたからです。
この活動をきっかけに、従業員のみならず管理職も時代に即した働き方への理解をさらに深め、新しい視点で働き方改革に取り組んでいけたらと思っています。
インタビューを終えて
「働き方改革プロジェクト」として、従業員がより良い職場環境を目指して進めてきた取組のひとつがテレワークの制度化でした。
IT企業において、テレワークは管理職にも従業員にも受け入れられやすいイメージがありました。しかし制度を浸透させるためには、さまざまな工夫や改善を粘り強く進めることが重要だと学びました。